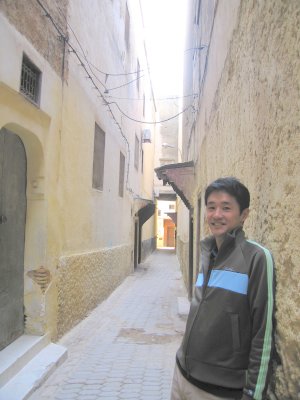今、新年度の始まりなので、キャンパスの至る所で、学生や教員、研究者の交流を深めるための、BBQや各種パーティ、スポーツ大会などが、連日開催されている。学生のサークルやスポーツ・クラブが中心でなく、大学本部や各部局の主導によるイベントが沢山用意されているところが興味深い。
今、新年度の始まりなので、キャンパスの至る所で、学生や教員、研究者の交流を深めるための、BBQや各種パーティ、スポーツ大会などが、連日開催されている。学生のサークルやスポーツ・クラブが中心でなく、大学本部や各部局の主導によるイベントが沢山用意されているところが興味深い。自分が今まで関わってきた日本の大学では、「入学者向けオリエンテーリング」以外に、大学主催の学生・研究者交流会はほとんど用意されていなかった。少なくとも自分は、研究室単位での“新メンバー歓歓迎会”以上の規模のものを経験したことはない。
ハーバードで7ヶ月間過ごす中で、このような大学・学科主催の「交流イベント」が多いことは常に驚きであるが、それと同時に、学生に対する大学のサポートがとても充実していることも日々感心している。
例えば、自分が所属する工学・応用科学研究科(SEAS: School of Engineering and Applied Sciences)では、全ての大学院生は完全なる金銭的援助(full financial support)を受けている。授業料は全額免除の上、毎月2,300USD(約25万円)の生活費がSEASから支給される。加えて、能力・働き次第で+αが研究室から上積みされることもある。学科(例えば、下のEPS)によっては、出身地からボストンまでの往復の航空券も支給する。ある学生曰く、「貯金ができる」とのこと。
そんな好条件での大学院入学に加えて、入学後のサポートも手厚い。
例えば、SEASが所属する教養大学院(GSAS)に入学した外国人の学生は、ハーバード・エクステンション・スクールが提供する英語の授業を50時間まで無料で受講できる(ちなみに、エステンション・コースの授業を普通に受講するとかなり高額!)。加えて、GSASでは、外国人の学生を対象に、論文の書き方を指南したり、レポートや論文・研究費申請などの研究の遂行に関する英文を添削する専属のスタッフまで雇っている(The Writing Center)。
 これは米国の研究大学では当たり前のことなのか、ハーバード特有のなのか分からないが、外国からやってくる大学院生にとってはとてもありがたい支援制度だ。学生ではない自分はこの制度を利用できないが、とても残念だ!
これは米国の研究大学では当たり前のことなのか、ハーバード特有のなのか分からないが、外国からやってくる大学院生にとってはとてもありがたい支援制度だ。学生ではない自分はこの制度を利用できないが、とても残念だ!将来誰かに、「日本と米国の大学院、どちらに行くべきか?」と問われたら、自分の場合、間違いなく米国を勧めるだろう。もちろん、日本で有利に就職したいのなら話は別だけど、純粋に教育や研究の環境を考えると、「(現時点では)米国に敵わない…」というのが現時点での正直な印象だ。
ちなみに、自分の知る限り、SEASに日本人学生はいない(2008-09の入学者は分からない)。
理学系のDepartment of Earth and Planetary Sciences(EPS)でも日本人学生は一人だけ。EPSのある先生から聞いた話では、「中国や韓国からはものすごい数の入学志願があるが、日本からは問い合わせすらほとんどない」とのこと。そして、「日本の大学でそれなりの成績を取っており、(事前に、受入先教授と相談の上)明確な研究計画書を用意できれば、合格の可能性も高いのでは?」と仰っていた。
 やる気はあるけど、お金の問題で大学院進学を断念しようとしている人は、いっそのこと、米国の研究大学に挑戦するのが良いのでは?もちろん、大学からの支援が手厚い分、入学後の生き残りは厳しく、学位取得もそれなりの時間を要するみたいだが、いわゆる“雑用”は存在しないため、研究に専念できるという。基本的に日本人は優秀なので、やる気と体力、覚悟を持っていれば、米国の研究大学で十分にやっていけるだろうから、ハーバードなどに積極的に応募するのが良いのではないだろうか?
やる気はあるけど、お金の問題で大学院進学を断念しようとしている人は、いっそのこと、米国の研究大学に挑戦するのが良いのでは?もちろん、大学からの支援が手厚い分、入学後の生き残りは厳しく、学位取得もそれなりの時間を要するみたいだが、いわゆる“雑用”は存在しないため、研究に専念できるという。基本的に日本人は優秀なので、やる気と体力、覚悟を持っていれば、米国の研究大学で十分にやっていけるだろうから、ハーバードなどに積極的に応募するのが良いのではないだろうか?(自分は日本の大学で学位を取得したので、こちらの大学がどれだけハードなのかよく分かっていません=僕の意見はほとんど参考になりません(笑)。でも、こんな情報を知っていたら、挑戦だけでもしただろうなぁ。)
さて、ハーバードの学生に対する研究・教育支援を書きだしたらキリがない。
ここの学生たちは本当に恵まれて環境で教育を受け、研究を進めている(もちろん、かなりの犠牲を払ってここまでやってきているし、ここでも相当の努力し続けていますが)。特に、学部生に対する支援や機会の提供は特筆すべきものがあるが、書ききれないで断念する(笑)。それよりも、自分が書きたかったのは、「ポスドク支援」だ。前ふりとして大学院生支援のことを書くつもりが長くなってきたので次へ続く(⇒「ポスドク支援」)。
≪写真・上 新学期で学生があふれるキャンパス≫
≪写真・中・下 楽しげなイベント盛りだくさん!自分も学生になりきり(!?)、図々しく潜入≫
↓ 学生でない自分は、上述のHarvard Writing Centerのリソースを使えないので、学外のESLでWritingを習うことに。そこの先生曰く、「長年教えてきた経験から、↓の本が外国人研究者・大学院生にWritingを教えるのに最も適している」とのこと。